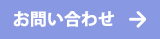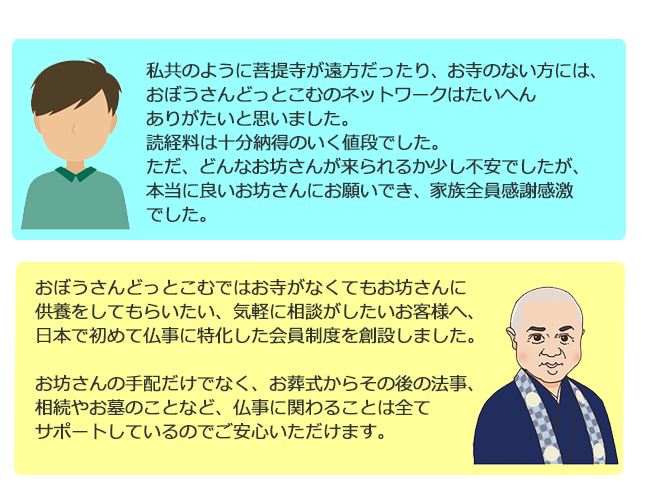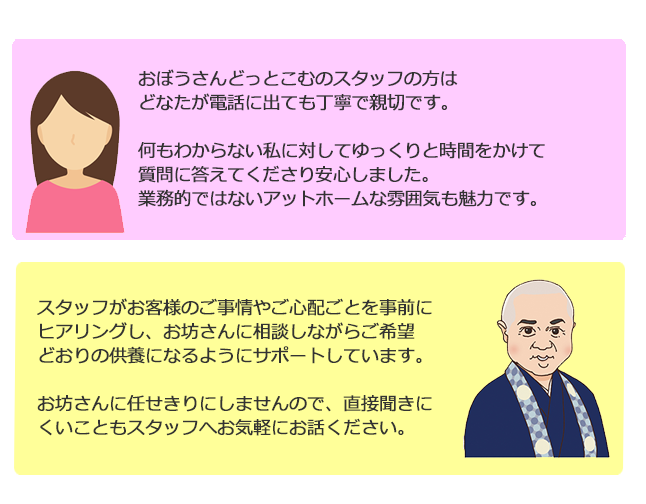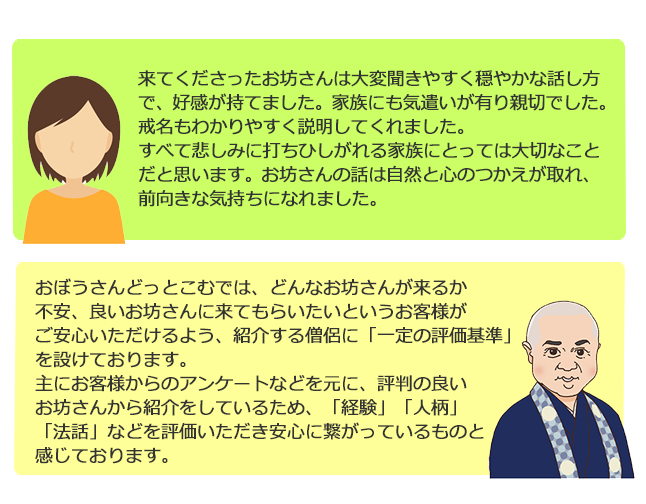通夜・葬儀に関する質問
通夜・葬儀において皆様よりご質問が多い項目についてまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください(質問における回答はあくまで一例です。必ずしもそのように行わなければならない、というものではありません)。
葬儀のことを生前に相談したいのですが、どうしたらいいですか?
「おぼうさんどっとこむ」では、無料で事前相談を承っております。
ご葬儀についてのご相談からお見積もりや不安・疑問まで、お気軽にご質問ください。
まずはフリーダイヤルもしくは事前相談ページから、ご希望の日時などをおしらせください。
専門スタッフが、お電話もしくはご都合のよろしい場所(ご自宅その他ご希望されるところなど)へお伺いし、事前相談をさせていただきます。
万が一の場合はどうしたらいいですか?
万が一、事が起こってしまった場合は、おぼうさんどっとこむのフリーダイヤル0120-056-594までご一報ください。ご連絡いただいた時点より病院等へのお迎え、搬送、ご安置から式場手配、火葬場の予約などお葬式に関わる全てのお手伝いをさせていただきます。
おぼうさんどっとこむに一報を入れた後の流れを教えてください
1.医師より死亡診断書(故人様の「死亡」を法的に証明する書類)をもらう
⇓
2.故人様のお迎え(おぼうさんどっとこむ専任担当者による)、搬送(寝台車)、ご安置
⇓
3.死亡から7日以内に役所へ届け出
※届け先は「届出人の現住所地」「死亡者の本籍地」「死亡地」の市区町村役場のいずれかに提出(届出人の認印が必要)。原本は提出するためコピーを取っておく。
※役所への届け出については、「おぼうさんどっとこむのお葬式」では、代行費用までをプランに含んでご提供しております。
⇓
4.お式当日までの期間において、お打ち合わせとご遺体のご処置等を行ない、葬儀当日を迎える。
※基本、2.以降の対応につきまして、おぼうさんどっとこむにお任せいただく際は、お客様とご相談の上、随時進めさせていただきますのでご安心ください。
葬儀会社を決めるポイントを教えてください
葬儀会社を選ぶ際には、必ず複数の葬儀会社から事前に見積書をもらい、比較検討することをお勧めします。
もし、取り寄せた見積書を見ても検討が難しい場合は、おぼうさんどっとこむにご相談ください。専門スタッフが取り寄せた各見積書の比較を分かりやすく解説いたします。
おぼうさんどっとこむでもご葬儀の運営をおこなっております。また、事前の相談、見積書作成も無料で行なっておりますので、まずはご連絡ください。
葬儀費用はどれくらい用意しておいたほうがいいのでしょうか?
葬儀費用は、葬儀の規模や内容、行なわれる場所などによって変わるため一律ではありません。一般的に自治体が運営する式場は「5~10万円」程度、民間の式場は「10~30万円」など、利用する式場によっても幅があります。
「おぼうさんどっとこむのお葬式」の場合、お葬式に最低限必要なサービスや物品がセットになったプランをもとに、その他、僧侶読経料金、式場費や火葬費用、お客様のご要望によりおもてなし費用(料理や返礼品など)、生花や供花などの演出費用などが必要となってきます。
当社では必ずお見積書を提示しておりますが、葬儀に必要な全ての事項(葬儀セットプラン・僧侶読経料金・式場費・火葬費用・おもてなし費用・演出費用など)が含まれた見積書となっているので安心です。
費用に関しては不安になられるお客様も多いと思いますので、事前相談及び無料お見積りをご利用ください。
菩提寺がありません。葬儀はどのように進めることになりますか?
当社でご僧侶のお手配をさせていただきますのでご安心ください。お客様のご要望に応じて、明瞭な料金でご案内いたします。
ただし、宗派の指定をご希望になられる場合、ご葬儀の日程を決める前に当社までご連絡いただけると、お式までの日程調整等がスムーズに運ぶと思います。
深夜でも対応可能ですか?
はい、可能です。
万が一の時は24時間365日ご対応しますので、まずは当社フリーダイヤル0120-056-594までお電話をお願い致します。
なお、深夜の時間帯はガイダンスにての対応となっております。ご案内に従いまして、お電話の「1」を押して、担当者の電話につながるのをお待ちください。
ご不安かと存じますが、焦らずごゆっくりとご対応くださいませ。
葬儀の際に準備しておくとよいのものは何ですか?
死亡届を提出する際に使用する「印鑑」をご用意ください。また、死亡届に故人様と届け人の本籍地を記入する項目がありますので、調べておくと良いかもしれません。
その他、遺影写真に使用する「故人様らしさが表現されているお写真」をご準備ください。写真に関しては、生前に写真館で撮ったものをご用意される方もいらっしゃいます。印鑑と写真以外にご用意して頂くものは、必要に応じて担当スタッフよりご説明いたします。
故人様の安置場所はどのように用意すべきですか?
ご自宅でご安置が可能な場合は、まずはご安置に使用するお布団をご準備いただき、そのお布団にてご安置をさせていただきます。
ご自宅でのご安置が難しい場合は、式場や火葬場に併設されている霊安室、もしくは当社で提携している各地域の霊安室がご利用になれます。
喪主は誰が務めるのですか?
一般的には、配偶者や子、兄弟など故人様と最も血縁関係や親等が近い方が、家族親族の代表として務めます。
葬儀は「友引」にはできないのですか?
友引には「死者が友を引く」から葬儀は行ってはいけないなどの諸説から葬儀を避けることもありますが、全国的には友引の日は火葬場のメンテナンスのため休場になっていることが多く、ご葬儀が行なえないこともございます。
ただし、自治体によっては友引でも火葬場が開場されている場所もありますので、その場合は行なう事が可能です。
葬儀のお布施はいくら必要ですか?
一般的には、お布施は「お気持ちで」渡すものとなっています。ですが、地域やお寺ごとにある程度基準になる金額があるようです。菩提寺がある方は、菩提寺のお寺に訊いてみると良いでしょう。
菩提寺のない方は、おぼうさんどっとこむにご相談ください。お客様のご要望によって明瞭な料金を定めていますので、いくら必要か不安にならずにすみ、安心です。
お布施は白黒の水引がついたお布施袋に入れて渡すのが一般的ですが、おぼうさんどっとこむの場合は特にを定めていませんので、封筒などに納めて担当僧侶にお渡しください。また、事前のカード決済(スクエア決済)及び振込でのお支払いもお受付しております。
お通夜やお葬式の服装などで気を付けることはありますか?
華美な色は避け、黒を中心としたモノトーンの色でまとめましょう。透ける布や光る素材も避けたほうが無難です。
通夜→モノトーン(黒・濃いグレーなど)のスーツやワンピース
葬儀→男性はブラックスーツ、女性はブラッフォーマルを着用しましょう。
※子どもの場合は制服またはモノトーンのフォーマルウエアが相応しい
※仏式の場合は数珠を持参するのが好ましい
※香典は袱紗に包んで持参すること
お葬式の際の、供花の芳名札の順番はどうしたらいいですか?
芳名札は故人様と縁の深い順番にしておきます。名前の間違いがないかどうかは、必ず確認しておきましょう。
焼香をする順番は決まっているのでしょうか?
喪主様から故人様と血縁が深い家族親族へと順番に行います。その後、知人友人などの一般会葬者の方にお焼香をいただきます。
焼香や玉串奉奠、献花の作法を知りたいのですが
作法は宗教によって異なります。下記に作法をまとめましたので、ご確認ください。
【仏式の場合→焼香】
(1)ご遺族に向かって一礼
(2)焼香台に行き遺影へ一礼
(3)抹香を右手の親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ
(4)軽く頭を下げた姿勢のまま、目のあたりまで持ち上げる※宗派によって異なります
(5)香炉の中に抹香を静かに落とす(1回~3回繰り返す) ※宗派によって異なります
(6)合掌
(7)一歩さがって遺影に一礼後2、3歩下がってご遺族へ一礼する
【神式の場合→玉串奉奠】
(1)ご遺族および神官に一礼
(2)神官から玉串を受取り一礼する
(3)玉串は、榊を上から右手で持ち、左手は葉の下に添える
(4)祭壇に進み、玉串を胸の高さに上げて一礼
(5)玉串を時計周りに回し、枝元を自分の方に向ける
(6)枝元を右手で下から持ったあと、枝元を左手に持ちかえ、さらに時計回りにして枝元を祭壇に向け玉串を供える
(7)1、2歩下がって遺影に二礼二拍手一礼
(8)ご遺族や神官、遺影に一礼
【キリスト教の場合→献花】
(1)花を受取る
(2)花の部分を右手にして両手で受取る
(3)祭壇前に進み一礼
(4)茎側を祭壇の方へ向けて置く
(5)遺影を仰ぎ黙とうを捧げる
(6)遺影に一礼、ご遺族に一礼
火葬時に必要なこと、マナーを教えてください
火葬時に必要なものは火葬許可証です。まずは地元の役所に死亡届けを提出し火葬許可証をもらってください。
葬儀が終わりましたら、火葬場から埋葬許可証を受け取ります。当社では火葬許可証取得手続きを代行しておりますのでご安心ください。
【火葬のマナー】
・拾骨は、喪主様からご遺族・近親者など故人様と縁の深い順番で、2人1組となって1つの骨を骨壷に入れます。使った箸は次の組に渡します。この作法には「この世とあの世の橋渡し」という意味があり、三途の川を皆で渡し、送ってあげようという気持ちを表します。
浄土真宗などは一般的には行わないなど、宗教・宗派によって違いはあるようです。
【注意するポイント】
- お骨は、生前同様の姿でおさまるため、足のほうから拾います
- 分骨が必要な場合は、火葬場の管理者が発行する分骨証明書が必要です。また分骨用骨壷等の用意が必要となります
遺骨を迎える際に自宅ですることはありますか?
部屋の片付けと後飾りの祭壇準備をしましょう。後飾りの祭壇とは、忌明け(49日)までの仏壇に納められない位牌や遺骨を安置する場所となります。
後飾りの祭壇は葬儀会社にお願いすることが来ます。もちろん、当社おぼうさんどっとこむでもご用意ができますので、必要な際はご依頼ください。
故人との対面の仕方はどうすればいいのですか?
故人様の枕元で一礼をし、ご遺族が白布を外して初めて故人様とご対面となります。終わったら合掌一礼をし、少し下がってご遺族に対して一礼をして退席しましょう。
また対面することを控えたい場合は断っても構いません。
受付を頼まれたのですが、何をするのでしょうか?
お通夜・葬儀・告別式での受付は、会葬帳・香典記帳簿・供物記帳簿・筆記用具などの準備をするとともに会葬者の記帳、香典などの受付を行います。受け付けた香典は会計係に引き渡されます。
弔辞を頼まれました。どうしたらいいですか?
弔辞とは、告別式のときに故人様を偲びお悔やみの言葉を捧げるものです。弔辞を書く際は、故人様の死に対する哀悼の意を述べるともに、故人様の業績や人柄、残された者の決意、ご遺族への励ましなどを綴り冥福を祈ります。文量としては、400字詰めの原稿用紙で2~3枚くらいに収まる長さを目安にすると良いでしょう。葬儀の宗教形式が不明の場合は、「浄土へおもむく」「天国へ行かれる」といった特定の宗教用語の使用は控えた方が良いでしょう。
弔問できない場合はどうしたらいいですか?
弔問できない場合には弔電を打ちましょう。弔電は葬儀や告別式の前日までに届くように手配します。宛先は喪主様または故人様の名前を書き、続けて「ご遺族様」と加えましょう。
115番に電話をかけ「弔電」と指定すれば、すぐに送ることが可能です。最近ではインターネットからの依頼も可能。定型の文例を参考にすることもできます。
御香典を包むときの注意点を教えてください
不祝儀袋での表書きをしますが、表書きは宗教によって異なりますので、宗派の形式に合わせて選ぶ事が大切です。
【仏式】
表書きは「御霊前」「御香典」
水引は黒白の双銀の結び切り
【神式】
表書きは「御霊前」「御榊料」「玉串料」
水引は黒白か白または双銀の結び切り
【キリスト教】
表書きは「御霊前」「御花料」(共通)、「御ミサ料」(カトリック)
ユリの花や十字架の描かれたものはキリスト教専用。
※一般的に、御霊前は通夜・葬儀時、御佛前は法事(法要)に使います。「御霊前」はどの宗派でも共通して使えます。
香典の金額の目安が知りたいです
故人様との関係や贈る側の社会的地位によっても金額が異なります。
下記は一般的な相場です。
※あくまでも目安としてお考えください。地域によって風習が異なるため実施には違う場合が多々あります。
【故人様が祖父母の場合】
20代→1万円~3万円
30代→1万円~3万円
40代以上→3万円~5万円
【故人様が両親の場合】
20代→3万円~5万円
30代→5万円~10万円
40代以上→5万円~10万円
【故人様が兄弟・姉妹の場合】
20代→2万円~3万円
30代→3万円~5万円
40代以上→3万円~5万円
【故人様が叔父・叔母の場合】
20代→1万円
30代→1万円~2万円
40代以上→1万円~3万円
【故人様がその他の親戚・友人・知人の場合】
20代→3千円~1万円
30代→5千円~1万円
40代以上→5千円~1万円
【故人様が隣近所の場合】
20代→3千円~5千円
30代→3千円~5千円
40代以上→3千円~5千円
お通夜の受付でのマナーを教えてください
まず受付では「この度はご愁傷様でございます」と一言挨拶をしましょう。
ここでのお悔やみは手短に済ませます。
また代理人として弔問し受付で記帳する場合には「代理記帳」となります。たとえば夫の代理として参列の場合、夫の氏名を記載後その左下に小さく「内」と書くのがマナーです。
香典返しはどれくらいが相場ですか?
一般的に「半返し」と言われ、お包みいただいた香典金額の半分程度の品物を送る事が多いようです。
納骨のマナーを教えてください
納骨には、喪服で行くのが望ましいでしょう。
宗教や宗派はどうやって確認するのでしょう?
まずは兄弟や親戚などに確認するとよいでしょう。それでも分からなかった場合には、自宅の仏壇や位牌で判明する場合もあります。
※お困りの場合は、まずは当社までご相談ください。
身寄りがなく葬儀費用を払ってくれる親族が居ない場合にはどうすべきですか?
友人・知人の方にお願いをするか、または司法書士や自治体の役所に相談し後見人を立てて頂くのが良いです。ご不明な点がございましたら一度「おぼうさんどっとこむ」までご相談ください。
提携する士業の先生方をご紹介いたします。
生活保護を受けていた場合、何か特別な対応が必要ですか?
まずはお住まいの地域にある役所の福祉課へ事前にご相談をされることをおすすめします。そこで葬祭扶助が支給されるかどうかをご確認ください。必ずご葬儀を行う前に葬祭扶助の支給決定を受けましょう。
※ご葬儀が終わられた後では葬祭扶助を受けることはできませんのでご注意ください。
家族葬と一般葬、一日葬、火葬式の違いは何ですか?
一般的には以下のような区分で分けられています。
【家族葬】家族や親戚およびごく親しいご友人など参列者をご遺族側で限定してお見送りするお葬式です。
※参列者を制限するお葬式のため、家族葬でも「通夜葬儀」「一日葬」「火葬式」と様々あります。
【一般葬】家族に加えて友人やご近所の方、会社関係者など多くの方と見送るお葬式です
【一日葬】お通夜は執り行わず、1日で葬儀告別式・初七日法要・火葬を行うお葬式です
【火葬式】式場は借りずに、火葬炉の前で最後のお別れのお時間を設け、荼毘(火葬)に付されるお葬式です
密葬は地元の葬儀会社、社葬は別の葬儀会社と、分けて依頼することは可能でしょうか?
葬儀会社には、地元密着型の葬儀会社から大規模葬を得意とする葬儀会社まで、様々なタイプの業者があります。そのため密葬は地元の葬儀会社、社葬は大規模葬に対応可能な葬儀会社と分けることは全く問題ありません。
おぼうさんどっとこむでも、密葬から社葬までのすべての葬儀式に対応が可能です。いろいろとご相談ください。
一日葬はどの葬儀会社も対応していますか?
すべて葬儀社さんで対応してもらえるわけではないようです。まずは葬儀会社に問い合わせてみると良いのではないかと思います。
「おぼうさんどっとこむ」でも一日葬には対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
語句に関する質問
葬儀や法事に関する語句において皆様よりご質問が多い項目についてまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください(質問における回答はあくまで一例です。必ずしもそのように行わなければならない、というものではありません)。
最近「エンディングノート」という言葉をよく耳にするのですが、具体的にどのようなものですか?
エンディングノートとは、自身に万が一のことがあった場合に、
・治療や介護、葬儀の希望
・財産分与
・大切な家族や友人に普段言えなかったメッセージ
・連絡リスト
といった内容を綴るリストになります。
最近ではインターネット上でも無料のシートを簡単にダウンロードすることも可能であり、エンディングノートをしたためることは、「自分の人生をどう過ごすのか?」「自分の最後をどう迎えるか?」といったテーマに向き合う良い機会にもなるでしょう。
ただし、エンディングノートには法的効力はありません。
湯灌(ゆかん)とは何ですか?
「湯灌」とは故人様の体を家族が集い洗い清めることです。
生前、個人が抱えていた苦しみやけがれを清め、故人様の来世の高徳を願って故人様にゆかりの深い人たちのみで行われる儀式となります。
手順や作法は地域によっても多少異なりますが、代表的なものとしては、
- 喪主様から順に遺体に逆さ水(=水にお湯を注いで温度調節をすること)をかけて清める。逆さ水をかける際、柄杓の持ち方は逆さ手(左手で柄杓の根元を持つ)を使う
- 足元からお湯をかけ、柄杓に残さないようにすべて使う
- 湯灌専門の納棺師が、立ち会い者全員を洗い清める
- ご遺体を布団に寝かせ、白装束に着せ替えたのち、全員でお線香をあげ終了
といったものがあります。
「白装束」と「旅支度」とは何ですか?
仏式の場合、葬儀では白装束と旅支度を直接着せたり、納棺の際に傍らに置いたりします。
「白装束」とは仏の弟子になるための衣装であり、「旅支度」とは四十九日間にわたる仏の世界へ行く旅に出るための支度のことです。
通常は、湯灌や納棺の際、遺族が二人一組となって手甲・脚絆・頭陀袋・六文銭・天冠・わらじ・つえをご遺体に着けます。近年では従来の白装束に代わり、故人様の愛用の服を着せるケースも多くなっています。
※浄土真宗では「お亡くなりになられた後、すぐに極楽往生する」という考えのため旅支度は不要です。
「納棺」とは何ですか?
納棺とは、枕経の後に遺体を棺に納める作業のことです。故人様の愛用品などを副葬品(可燃のもの)として入れることもできます。棺内には故人様のお体を保全するためドライアイスでの処置も一緒に行われます。
「枕団子」や「一膳飯」とは何ですか?
仏教では、亡くなってからあの世に行くまで四十九日の旅があります。そうした中、「枕団子」と「一膳飯」といったものは、故人様が道中に食べる食事または仏様への手土産などと伝えられています。
「枕団子」は上新粉で作られ、数は6個(六地蔵、六道輪廻にちなみ)か、49個(四十九日から)が多いようです。
一方「一膳飯」とは、故人様が使用していた茶碗にご飯を山盛りにし垂直に箸を立てたものです。これらは最終的には柩に納められるものになります。
※四十九日の教義がない浄土真宗などでは、枕団子や一膳飯は不要です。
「戒名」とは何ですか?
戒名とは、授戒し仏弟子になった証に名前を変えることで、今日では成仏の証として故人様に戒名を付けるのが一般的です。
戒名は「院号」「道号」「戒名(法号)」「位号」の4つに分かれており、一般には「●●院(院号)、●●(道号) ●●(戒名・法号) 信士(位号)」といった形で命名されます。
院号は、本来はお寺や社会に貢献した人に与えられるものです。道号は戒名の上に付ける字、戒名(法号)は故人様の人柄など、位号には信士、信女、居士、大姉(性別や年齢でも異なる)などがあります。
戒名は宗派によって特徴が異なり、浄土真宗では「戒名」と言わずに「法名」と呼んだり、道号・位号がなく「●●院釈●●」となったりするケースがほとんどです。
また日蓮宗では「法華信者は霊山浄土に生まれる」とされることから、戒名ではなく「法号」と呼ぶことが多いとされています。
「祥月命日」とは何のことですか?
祥月命日(しょうつきめいにち)とは、年に一回ある「亡くなった忌日」のこと。たとえば故人様が一月一日に亡くなったのであれば、毎年一月一日が祥月命日となります。
「通夜振る舞い」をする理由は何ですか?
通夜振る舞いは、弔問に対するお礼の場であり、食事をして故人様を偲ぶことによって故人様の供養になるとされています。また酒で体を清める意味もあり、ソフトドリンクだけではなくアルコール類も用意されます。
一説によると「通夜に料理を振る舞う=お清め」という意味も込められているようです。もし通夜振る舞いに誘われた場合には、ご遺族の心遣いに応えるためにも一口だけでもいいので箸をつけると良いかもしれません。
葬儀から帰宅後に塩を身体に振りかける理由は何ですか?
葬儀の際にもらう振り塩は、けがれ(=非日常の世界に行ったこと)を塩によって振ってはらうという意味があります。ただし、死をけがれとは考えないキリスト教や浄土真宗のように、宗教や宗派によっては使用しない場合もあります。
「エンゼルケア」とは何ですか?
エンゼルケアは、ご臨終の際に看護師などが行う処置です。
看護師は主に感染予防など医学的な観点に基づいて処置が行われますが、葬儀会社によるエンゼルケアは葬送儀礼の準備段階という位置づけとなっています。最近では、エンゼルケア自体を葬儀会社に依頼する病院なども増えてきています。また双方が連携を取って行うケースもあり、どのような分担・内容で行われるかはお世話になっている病院や施設へご確認ください。